
【プロフィール】
石井優衣さん(高校3年生)
中学2年生で横紋筋肉腫(※1)と診断された彼女は、約1年の闘病生活を乗り越え復帰するも、社会生活を送るうえでさまざまな困難もあるということを実感しました。小児がん経験者の交流会に参加したことをきっかけとして、経験者の代弁者として自ら声を上げる必要性を感じ、以来、積極的に啓発活動に取り組んでいます。
私は8・10・14歳差と、かなり歳の離れた弟妹が3人いる長女です。中学2年生で病気と診断されるまで、まだ幼いかわいい弟妹と過ごす時間が大好きでした。特に当時0歳の一番下の弟の成長は私の楽しみのひとつでした。その頃の私は、学校では毎日バレー部の練習に明け暮れ、家や公園では弟妹たちと遊び、家族旅行にも頻繁に出かけるという生活を送っていました。活発で誰とでもすぐに仲良くなれるタイプだったと思います。

そんなある日、不正出血がありました。あまり深刻に考えず産婦人科を受診しました。ただ、そのときは大量に出血していると検査ができないと言われたので、症状が治まるまではふだんと変わらず過ごすことにしました。けれどもその年の12月に家族で沖縄旅行へ行ったとき、体調が悪くて何もできなくなってしまったので、あらためて検査を受けることにしたのです。
そこで言われたのは、「子宮の大きさが通常の2倍」ということでした。がんではなさそうだが念のためと精密検査を勧められ、紹介状をいただいたので、そのときも「そういうものなんだ」程度の気持ちでした。その後、精密検査前に体調がさらに悪化し、重度の貧血で仮入院しました。がんだとは夢にも思っておらず、初めての入院にワクワクしていました。実は、その時点で両親は病名を知っていたようです。
自分にとって、がんは遠い存在で、「がん=死」というイメージでした。そのため、転院先で病名を告げられたときはショックでそのあとの説明が頭に入ってきませんでした。ひととおり説明してもらったあとで先生から「何か聞きたいことある?」と聞かれましたが、ただ「ありません」と答えるしかありませんでした。説明のあと、CLS(※2)の方が来てくださって、病気の状況や今度の治療について目を見てゆっくりと話してくださいました。そこでようやく自分の状況が整理できました。
多くの友人には病名は告げず、ただ1年近く入院することになったと伝えました。一部の仲の良い友人にのみ、小児がんであることを伝えましたが、彼女たちの周りには私のほかに小児がんの子がいるわけもなく、大変さやつらさを想像してもらうことはできないだろうなと思っていました。心配をかけたくなかったですが、一方で気遣ってもらいたいような、そんな複雑な気持ちでした。ありがたいことに、友人からは「大丈夫?」というメールが届いていました。そこでは「大丈夫!」と答えていましたが、実際には大丈夫な瞬間などなかったです。それでも、私のことを気にかけてくれていると思うだけで嬉しかったです。一方で、友人たちはふだんと変わらない生活を送っており、皆の楽しそうなインスタグラムの投稿を見るのはとてもつらかったです。私もそれまでは一緒に楽しんでいたことがまるで別世界のように感じ、私だけが取り残されたようで、孤独を感じました。

また体力の衰えがひどく、トイレまで歩くこともできない、ペンすら持てないなど、予想以上でした。もちろん好きな物を食べられないし、家にも帰れない、家族や友人にも会えない。外の空気さえ吸えず、季節を感じることもできませんでした。また、周りの友達がおしゃれに気を遣い始めた影響で、私も髪を伸ばそうと思っていたところに脱毛したこともつらかったです。普通に享受していた当たり前のことが、どれも当たり前ではなくなり、特別なものとなりました。
抗がん剤の治療も想像を絶するものがありました。「この治療を受けるくらいなら死んだほうがまし」と何度も思いました。生きるための治療なのに死を選びたくなるあの苦しみを、できれば誰にも経験してほしくないと思います。また一方で、病院の入院仲間は私と同じようなつらさや苦しみを共感できる一生の仲間となりました。同じつらさに立ち向かっている仲間の存在にとても勇気づけられました。仲間内では私が年長者でしたので、一方的に悩みを聞くことが多い立場でしたが、生きる意味を感じられました。また、退院後に「ピアサポート」という言葉を知りましたが、まさに、お互いにサポートしあいながら苦難を乗り越えていくことに、医療従事者の方々からの支えとはまた違う力をもらいました。
がん治療を終えても、その影響は続きました。まず、体力がなかなか戻らず、通学のバスや電車の揺れだけで倒れそうになっていました。見た目は普通の学生なので優先席を利用しづらく、途中下車して駅のベンチで休憩しながら通学していました。ウィッグを被っての生活もとてもつらいものでした。風の強い日はそれだけで通学が憂鬱になりましたし、体育の授業では「見た目は元気なのに見学する」ことへの後ろめたさを感じました。夏の暑い日には頭から大量の汗が出ます。あんなにも切望していた「普通」が、小児がんを経た私にとっては過酷でした。
長期の入院で学力も下がり、授業にもついていけず、自宅で必死に復習する毎日でした。みんなが部活や遊びを楽しんでいる間、なぜ自分だけが……と何度も思いました。それまでの活発だった性格は影をひそめ、次第に自分を見られたくない、隠れたいと思うようになっていきました。
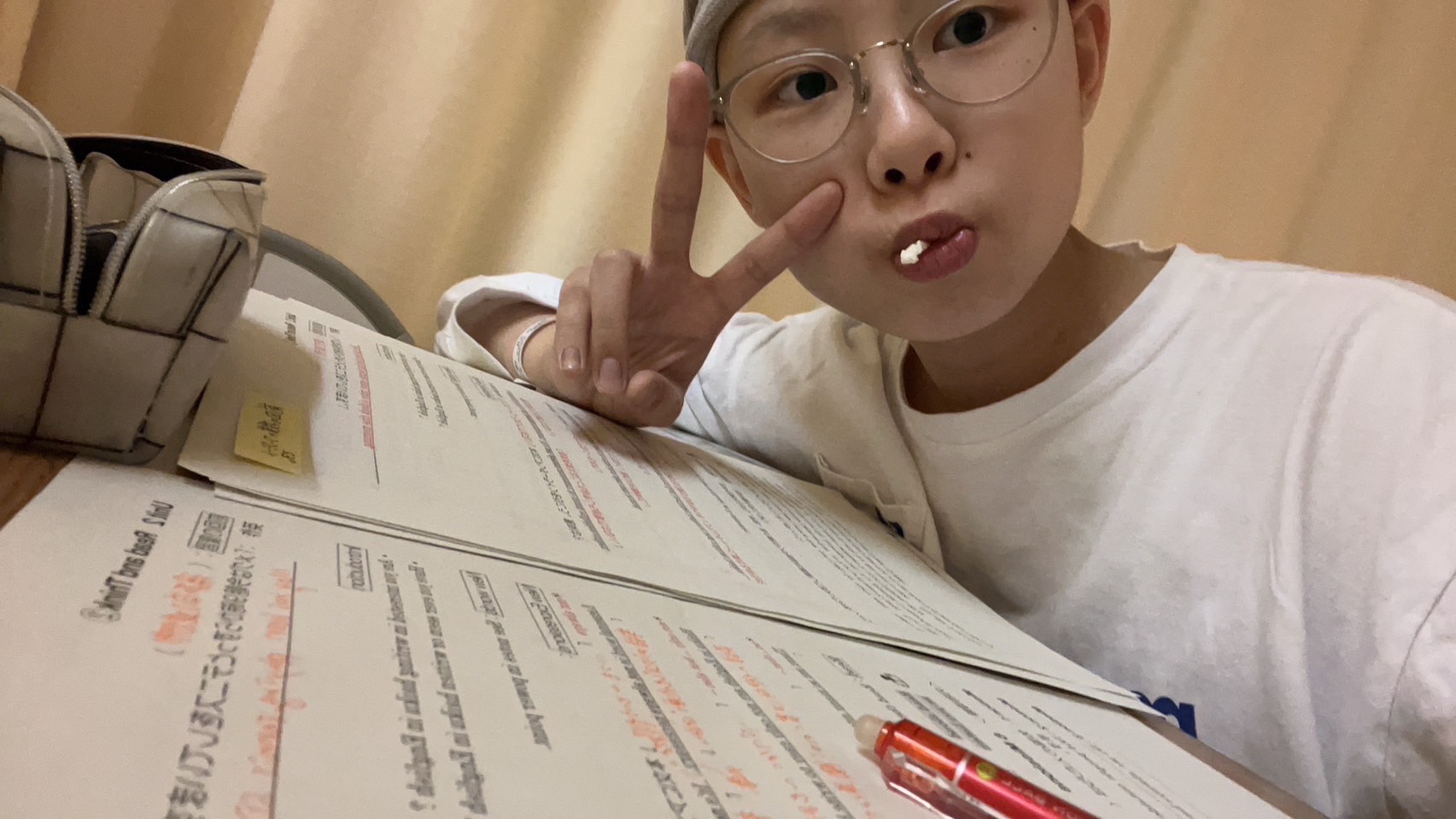
そんな折、初めて小児がん経験者の交流会に参加しました。皆病名は違っても抱えている悩みは同じでした。社会になじめない、孤独を感じる、誰も理解してくれないなど、退院後もずっと苦しんでいる人が大勢いることに驚きましたし、自分だけではないと思えるようになりました。また、その頃ようやくウィッグを被らずに通学できるようになり、少しだけ入院前の自分に近づいた気がして、前向きになれました。交流会をきっかけにして、皆のこの苦悩や生きづらさを代弁できれば、もっと生きやすい社会になるのではと考えるようにもなりました。そのときあらためて自分の入院中や退院後の生きづらさについて振り返り、自分と向き合う時間を持ちました。
生きづらさを感じながら社会の一員になろうと頑張っている仲間や、亡くなっていった仲間、抗がん剤でつらい思いをしている闘病中の仲間のためにも、自分が何かをしなくては! 思うだけではなく行動をしなくては! 皆のために社会を変えたい!と思うようになりました。この気持ちの変化には、自分が一番驚いています。
この春、厚生労働省に要望書を提出しました。自分一人の声に大した力はなくても、行動したい一心でした。予想外の反響があり、内閣府副大臣の公式動画にも出演させていただきました。行動することで何かが変わる可能性を感じました。
ゴールドリボンウオーキングでも、小児がん経験者の方々から、気持ちを代弁してもらえたようで嬉しかったという言葉をもらいました。また、闘病中の子や退院後の子たちに、仲間がいること、孤独ではないことを伝えられたような気がします。

自分のこれからについてお伝えしますと、小児がんについての啓発活動を続けながら、退院後も生きづらさを感じ続けている子たちのための支援活動もしていきたいと考えています。治療後、どんな障がいが残っても、どんな晩期合併症があっても、安心して戻れる社会を作ることが私の目標です。そのために解決しなければならない課題はたくさんあります。医療の力で救っていただいた命があるかぎり、当事者である私が声を上げ、社会を変えていくことを使命として活動を続けていきたいです。
(※1)筋肉などの軟らかい組織(軟部組織)から発生する軟部肉腫の一つで、将来、骨格筋(横紋筋)になるはずの細胞から発生した悪性腫瘍 (出典:がん情報サービス)
(※2)チャイルドライフスペシャリスト。病気や医療体験における子どもへの支援として、その子どもの発達に応じた説明や理解の援助、きょうだいを含むご家族の心理社会的サポートを主に行う
